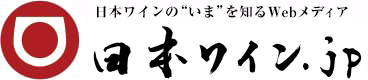魚卵独特の風味とプチプチした食感がたまらない加工食品、「数の子」。
お正月に食べるおせちや寿司ネタとして、または松前漬けなど日本人が愛する食材のひとつです。
しかし、この数の子。
ワインとの相性がすこぶる悪く、「天敵」と見なしている人がいるとかいないとか…。
ここでは、ある種の都市伝説にもなりかけている、「数の子に合うワインはない説」は本当か検証していきたいと思います。
数の子のスペック

数の子とワインについて考える前に、まずは数の子のスペックを確認していきましょう。
数の子とはニシンの魚卵のことで、ニシンが生育するための必要な栄養分が凝縮されている栄養たっぷりな食材です。
株式会社加藤水産によると、数の子は水分を除く82%がたんぱく質で14%が脂質(脂質の72%はリン脂質)からなっており、脂質に占めるEPA・DHAの割合はなんとマグロのトロ以上。
抗肥満効果や血糖改善、血中脂質改善など機能性に優れているだけでなく、気になるプリン体も豚レバーやウナギ、ほうれん草などと比べて極めて少ない(100g中の総プリン体の量において〜50mg)など、体に優しい食品のひとつとされています。
そんな数の子ですが、ワインとの相性を見る時にひとつ注目すべきが「EPA・DHA」。
ワインと数の子が合わない…といわれている理由の秘密がこのEPA・DHAに隠れているようです…。
DHAやEPAと亜硫酸が相性悪い説

以前、(独)酒類総合研究所と日本酒酒造組合中央会との共同研究で白ワインや清酒とシーフードとの相性を検証する研究が行われました。
まず、魚介類の生臭みの要因がDHAやEPAです。
これらは多価不飽和脂肪酸と呼ばれているのですが、DHAやEPAの酸化によって生成されるカルボニル化合物が生臭みの原因だと考えられています。
初心者には少々難しい研究なので詳しくは省きますが、研究者によると亜硫酸やクエン酸、リンゴ酸などをそれぞれ清酒やワインに加えていき、そこにDHA添加により苦みや臭みなどの数値を検証していったそう。
結果、亜硫酸を添加した溶液だけが臭みと苦みを感じさせる数値を出したと示唆されています。
亜硫酸だけが要因ではないと最終的に示唆しているものの、研究結果後にパネリストたちにDHAやEPAたっぷりの焼アジを肴に亜硫酸を添加したワインと亜硫酸無添加ワインの2つで官能評価してもらった結果、亜硫酸添加ワインの方が相性が悪かった…という結果となったようです。
数の子もDHAやEPAが豊富である上にほとんどのワインには亜硫酸が入っていることから、相性が悪く感じてしまうのかもしれません…。
鉄分が要因説

数の子とワインの相性が悪いのなぜか。
あとひとつの説が、「ワインの鉄分が魚介との相性を悪くする」というものです。
なかなか有名な話なので知っている方も多いかもしれません。
この話はメルシャンの田村氏が研究によって発見したもので、酸化されたEPAとDHA(過酸化物)と鉄分がぶつかると生臭みを感じる…という研究で、概略すると「ワイン中に含まれている鉄分が魚介類がもつ酸化されたEPAとDHA(過酸化物)と組み合わさることにより、生臭みを感じやすくなる」というものです。
ただし、田村氏いわく「酸化されていない新鮮な魚介類であれば生臭みを感じにくくなる。また、オリーブオイルやバターを使ったりレモンや調味料をふりかけるなどすることで生臭み自体が中和されるためワインと合いやすくなる」と言っています。
とはいえ新鮮な数の子を手に入れることも難しいでしょうし、数の子を大胆にアレンジして食べるほど数の子に飢えている方が多いとは思えません…。(そこまでしてワインと合わせたいか…)
そうなると手段としては、「数の子にワインを寄せていく…」という考え方が正しいかもしれません。
数の子に合うワインの要素は?

亜硫酸と鉄分。
この二つのポイントをクリアしたワインであれば、数の子との相性がよくなるかもしれません。
まず亜硫酸ですが、そこだけに注目するのであれば本来はヴァンナチュールを選びたいところです。
オーガニックワインやビオディナミなどのワインもいいでしょうが、亜硫酸添加はそこそこ認められている上に醸造上の観点から添加物もそこそこ入れてよいことになっています。(ただし、発酵中に亜硫酸は必ず発生するため、実際には全てのワインに含まれています)
とはいえ、亜硫酸は基本的に瓶詰め前に添加されたとしても数ヶ月で消えることがわかっているため、ある一定の熟成を経ているワインには遊離亜硫酸(実際にワインを守るために働いている亜硫酸)が残存していないと考えます。
ヴァンナチュールは品質に難アリものも多いですし…。
次に、鉄分。
はっきりとはわかりませんがブドウ畑の環境によって海外のワインは日本のワインに比べて鉄分が多いかもしれない…という話です。
もちろん全部が全部ではないでしょうが、日本は軟水であることや棚栽培なので土ホコリの影響を受けにくいため鉄分が入る余地が少ないということ。
鉄分ゼロのワインはないものの、海外のワインに比べれば甲州やマスカット・ベーリーAなどの方が魚介類に合わせやすい可能性があるわけです。
数の子にグレイス グリド甲州2015を合わせてみた

いろいろな要素から「数の子」に合うワインを考えた結果、やはり甲州が良かろう…という結論に。(勝手に)
アロマティック過ぎず香りが穏やかなもの、ある程度熟成されており遊離亜硫酸がほとんどないと考えられるもの、手に入れやすい価格であること…。
この要素を満たしている、中央葡萄酒の「グレイス グリド甲州2015」と数の子を合わせてみました。
白ワインでありながら若々しくフレッシュな香りと風味を維持しているだけでなく、グリ系ブドウらしい厚みのある味わいも魅力的な1本です。
さて、まずはシンプルに数の子に何もかけずにペアリング。
口の中で数の子とワインが混じり合った瞬間、「げ…。ここから嫌な臭みと苦みが来そう…」と恐怖を感じたものの後味にむしろ爽やかな余韻が残る好ましい組み合わせに。
さらにハードルを上げて鰹節をかけたバージョンで試したものの、むしろ鰹節の風味と数の子の風味、「グレイス グリド甲州2015」の風味が混ざり合い複雑で楽しいペアリングとなりました。(生臭みもありません!)
この後に日本酒との相性も確かめたのですが、日本酒のアルコール感や香りの要素が強すぎて食べ疲れてしまうという謎展開。
人の好みなので強制しませんが、個人的に「数の子×ワイン」に軍配が上がりましたね。
合う要素を探る!

ワインと数の子。
やり方によっては、「最悪な結果」にはならないことがわかりました。
当然、人によって何がペアリングにおける“成功の基準”かわからないのでアレですが、いろいろな組み合わせを全否定するのではなく、「歩み寄る姿勢」が大切かもしれません。
ワインの教科書やレストランに溢れている定番のペアリングを頭に叩き入れることは大切です。
しかし、それを覚えたらその情報に固執するのではなく、「次のステップ」にチャレンジすること。
これこそワインペアリングの醍醐味なのではないでしょうか。
今回は数の子でしたが、次はワインの強敵である納豆でもやってみようと思っています。
厳しい戦いとなることは想像に難くありませんが…。
参考