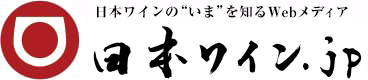昨年11月、池田町独自品種「山幸(Yamasachi)」が、「OIV(国際ブドウ・ワイン機構)」にリスト登録されました。
「OIV」にリスト登録されている日本のワイン用ブドウ品種といえば、甲州とマスカット・ベーリーAが有名ですが、山幸はそれに次ぐ3番目の登録。
日本ワインが世界から注目される、きっかけのひとつになったのではないでしょうか。
さて、そもそも「山幸」とはどんなブドウ品種なのでしょうか。
ここでは、OIVに登録された「山幸」について解説していきます。
山幸は十勝ならではの環境が生み出した品種

山幸は池田町で誕生した醸造用赤品種です。
池田町では1963年から国内初の自治体経営によるワイン醸造を開始していますが、同町が位置する北海道十勝は2月頃にマイナス20度に達するという極寒の地。
何らかの対策をしない限り、一般的なブドウは越冬できないといった課題を抱えていました。
そこで、耐寒性や収量性を目的にフランスの「セイベル13053」をクローン選抜。
1969年に醸造用赤品種、「清見」が誕生します。
山幸の誕生

「清見」は優れたブドウ品種であったものの、極寒の十勝を越冬するためにはさらに対策が必要でした。
そこで、池田町ブドウ・ブドウ酒研究所は海外から導入したブドウ品種と在来種である「山ブドウ」を交配した新品種の開発に着手。
さまざまな交配品種が誕生した中で、醸造用赤品種「山幸」と「清舞」が誕生しました。
今、「山幸」と「清舞」は北海道十勝を代表する重要な存在。
これら品種は北海道十勝だからこそ生まれた、土着品種といってもいいのではないでしょうか。
山幸の特徴

「山幸」は、「清見」と「山ぶどう6号園20オス」の交配から誕生したブドウ品種。
耐寒性や耐凍性に優れていることはもちろん、良質なワインを生み出すことでも知られています。(ちなみに、マイナス31度まで耐えられるとか)
山幸から造られるワインは色合いが濃く、渋みや味わいもしっかりとした印象。
山ブドウがベースにあることから、野性味も感じられるほかにない味わいを楽しむことができます。
一方の「清見」から造られるワインは色合いが淡く、渋みの少ない軽快なタイプ。
今回、ボディがしっかりとした「山幸」がOIVに登録されましたが、今後「清見」も期待できるかもしれません。
活躍の幅の広さも魅力

OIVへの登録ということで、ワインとしての「山幸」が今後注目されていくことは間違いありません。
しかし、「山幸」の魅力はワインだけではなく、さまざまな食品にも活用されているところ。
ケーキやゼリー、カレーなど、多種多様な食品に使える汎用性の高さに注目が集まっています。
とくに今、活用先として期待されているのが山幸酵母を使用した、パン製造。
山幸ブドウから酵母を純粋分離した山幸酵母を使用する場合、異性化糖を用いて製パンすることで風味の良いパンが製造できることがわかったとのこと。
さらに、ほかのパン酵母と比較すると時間と作業の手間がかかるものの、ふっくらと大きくてふんわりとした食感のパンが作れそうです。
近年空前のパンブームが到来していますが、山幸酵母が新しいヒット商品を誕生させる可能性があります。(山幸ワインとのペアリングも楽しみです)
「ワインとパン」といったキーワードに惹かれる方も多いでしょう。
ぜひ、ワインだけでなく、食品としての山幸にも注目してみてはいかがでしょうか。
山幸を飲もう!

OIVに品種登録されたことで、今後「Yamasachi」とラベルされたワインがEUへ輸出されることが期待されています。
欧州系のワイン用ブドウとはまた違った、独特な味わいの「山幸」。
ぜひ、日本ワインファンの方はチェックしてみてはいかがでしょうか。
参照